採用情報
お問い合わせ
2023年1月12日
|2023年5月16日
インフラエンジニアについてインターネットで調べると、「きつい」「やめとけ」「つまらない」などの関連用語が出てきて不安に感じている人もいるでしょう。インフラエンジニアに限らず、全ての職業には少なからず向き不向きがあり、向いていない職業に就いてしまうとつまらない、きついと感じてしまうこともあるかもしれません。
では、どんな人がインフラエンジニアに向いているのでしょうか。この記事では、インフラエンジニアという職業の説明を含め、インフラエンジニアの適性や魅力について説明していきます。
この記事の目次
 わたしたちがITサービスを利用するとき、画面に見えない部分では、情報通信のためにサーバーやネットワークといったITインフラが稼働しています。いわばITサービスを利用するうえでの土台となる部分であり、そのITインフラを設計したり、運用・保守したりしているのがインフラエンジニアです。
わたしたちがITサービスを利用するとき、画面に見えない部分では、情報通信のためにサーバーやネットワークといったITインフラが稼働しています。いわばITサービスを利用するうえでの土台となる部分であり、そのITインフラを設計したり、運用・保守したりしているのがインフラエンジニアです。
インフラエンジニアは広義な言葉であり、専門性が高まるにつれ、サーバーエンジニアやネットワークエンジニアといったように細分化して呼ばれることも多くあります。
業務内容は、設計・構築・運用・保守・監視の5つの段階に分けられ、それぞれの段階で求められる知識のレベルも変わってきます。基本的には、運用・保守・監視業務からキャリアをスタートさせ、知識を深めていくにつれて、構築や設計業務へのキャリアアップを目指せるようになっていきます。それぞれ、どのようなことをするのか簡単に説明しましょう。
システムに必要なITインフラを設計する業務で、高度な知識が要求されます。
システムの規模や通信量などを予測し、障害が起こらず安定して稼働するITインフラを設計します。
設計書に沿って、サーバーやネットワーク機器の調達、設置・設定を行う業務です。設計書通りに構築しても稼働しないこともあるため、現場で試行錯誤できる知識やスキルが必要です。
システムの稼働やセキュリティなどを監視し、もし障害が起これば対応します。監視やトラブル対応、定期的なメンテナンスといった保守業務だけでなく、システムのバージョンアップや顧客サポートなどの運用業務もセットで行うことが多くあります。
 「インフラエンジニアに興味はあるけど、どんな人が向いているんだろう?自分は向いているのかな」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、運用・保守・監視業務からキャリアをスタートしていくことを前提に、向いている人の特徴を7つご紹介します。すべて満たしている必要はなく、性格が不向きでも優秀なインフラエンジニアはたくさんいますので、あくまで興味を持つきっかけとして参考にしてください。
「インフラエンジニアに興味はあるけど、どんな人が向いているんだろう?自分は向いているのかな」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、運用・保守・監視業務からキャリアをスタートしていくことを前提に、向いている人の特徴を7つご紹介します。すべて満たしている必要はなく、性格が不向きでも優秀なインフラエンジニアはたくさんいますので、あくまで興味を持つきっかけとして参考にしてください。
未経験からインフラエンジニアを目指す場合、まずは保守業務の中でも監視から仕事を覚えていくケースが多くなります。
監視は安定したITサービスを提供するうえで、とても重要な業務ですが、単調な作業になりがちです。システムトラブルが発生しない限りは、日常的にマニュアルに従いシステムに異常がないかを点検する確認作業の繰り返しです。また、運用・保守の業務では、数多くのコンピュータに同じ設定作業を行ったり、毎日同じ時間帯にネットワーク確認を行ったりと単純作業が多い傾向にあるため、単純作業が好き・得意な人に向いていると言えるでしょう。
単純作業が得意でなくとも、単純作業を効率化できる人はインフラエンジニアに向いていると言えます。運用・保守で単純作業の効率化を考えられる人は、設計に携わった時に効率的でパフォーマンスの良い設計ができるでしょう。効率的な設計で作られたシステムは、作業負担を減らすだけでなく、複雑な処理によるエラー要因や人的ミスを減らすことができます。構築作業でも、段取りよく設置や設定を行える人の方が、落ち着いて作業ができミスは少なくなります。
ITインフラは24時間365日稼働しているため、運用・保守・監視を担当しているインフラエンジニアは深夜や土日でも、シフトによって出勤する必要があります。シフト通りの勤務で残業が少ない傾向にあることはメリットですが、トラブル対応などの際には、非番でも対応に向かわなければならない事態もありえます。そのため、不規則になりがちな勤務体制に対応できる人が向いていると言えます。
インフラエンジニアは、急なシステムトラブルや障害が発生したとき、パニックにならず冷静沈着に対応しなければなりません。回線やデータといったITサービスの土台部分を取り扱っているため、焦って誤った対処をしてしまうと、うっかりでは済まない大きなミスにつながってしまうこともあります。特に「どうしてこのような障害が起きたのか」「どこに原因があるのか」「どうすれば正常に作動するようになるのか」を順序だてて論理的に物事を考えられる人は、設計や構築などへのキャリアアップにも考え方を活かしやすく、向いていると言えるでしょう。
インフラエンジニアにとって、コミュニケーション能力は担当する業務に限らず重要となります。運用・保守・監視では、どのようなことが起こっているか整理し、トラブル対応できる部署へ早く適切に報告できるスキルが求められます。報告・連絡・相談ができることはインフラエンジニアとしての基礎的な能力です。
また、設計業務においても、ヒアリングをして顧客のシステムに対する要望をうまく引き出すためにはコミュニケーション能力が欠かせません。システム開発ではインフラエンジニア以外の職種の人と接する機会も多いため、コミュニケーション能力が高い人は向いていると言えるでしょう。
インフラエンジニアは、サーバー機器やネットワーク機器などのハードウェアを実際に取り扱います。運用保守の業務から、構築業務へキャリアアップを目指すなら、機器取扱のスキルアップが必要です。
取り扱う機器は、メーカーによって仕様も異なりますし、時期によって型が変わることもあります。様々な機器の設定や組立、接続などを行うため、普段から家電や機械をいじるのが好きな人やパソコンを分解して組み立てたりすることを趣味としているような機械を触ることが好きな人・機械に興味がある人に向いていると言えるでしょう。
設計に携わるインフラエンジニアは、顧客の要望に対応できるIT機器やサービスを提供しなければなりません。単純なパフォーマンスだけでなく、コストや保守方法などの要件も出てきますので、最適な情報を提供するためには、最新情報も含め広く情報を知っておく必要があります。また、IT機器には保守期限があるため、できるだけ長い期間保守できる提案のためにも最新の機器を選定する必要があります。そのため、日々更新される最新の情報を知りたい、技術を取り入れたいと思える知的好奇心があり、スマートフォンやパソコン、家電製品など新しいものが発売されるとすぐに欲しくなるような新しいもの好きな人に向いていると言えます。
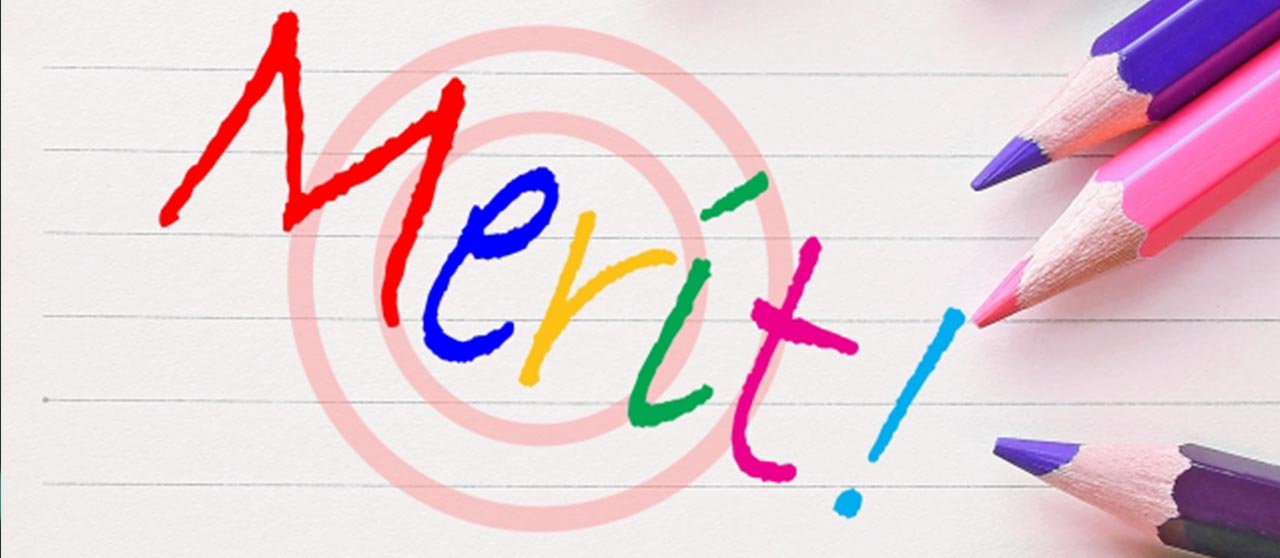 インフラエンジニアに向いている人の特徴について述べてきましたが、興味があるようでしたら、インフラエンジニアの魅力についても知っておきましょう。ここからはインフラエンジニアとして働くことのメリットについて3つご紹介します。
インフラエンジニアに向いている人の特徴について述べてきましたが、興味があるようでしたら、インフラエンジニアの魅力についても知っておきましょう。ここからはインフラエンジニアとして働くことのメリットについて3つご紹介します。
インフラエンジニアを含むIT業界の人材不足は深刻化しており、人手が足りないから、というのが未経験者採用の理由の一つとなっています。大手求人サイト「indeed」のキーワード検索で「インフラエンジニア」の求人はおよそ21万件あり(2022年12月15日現在)、「未経験」のキーワードを追加しても、およそ18万件もの求人があります。
インフラエンジニアに必要な知識・スキルや経験の有無よりも、入社後の成長スピードや伸びしろに期待し、研修制度を設けて未経験者を採用する企業は少なくありません。また、未経験から入社した場合、専門的な知識やスキルがなくても、マニュアル通りに対応しながら仕事を覚えられる、初歩的な仕事があることも理由の一つです。
ITインフラといっても、サーバーやネットワーク、セキュリティなど、専門にする領域には違いがあります。さらに近年ではクラウドや仮想化など新しい技術の登場により、インフラエンジニアの業務はさらに拡大してきました。スタートアップやベンチャー企業など、人員を多く雇用できない企業では、インフラ部分だけでなく、プログラミングの技術も身に着け、一人で複数の業務を担当するフルスタックエンジニアも活躍しています。
新しい知識や技術を身につけるための勉強は続けなければなりませんが、ITインフラの基礎知識をベースとして、幅広い知識やスキルに専門を広げ、自分のキャリアにつなげていくチャンスがあると言えます。
経済産業省が発表したIT人材需給のデータによると、ITニーズの拡大によってIT市場は今度も拡大の一途をたどり、2030年にはおよそ40万~80万人のIT人材が不足すると予測しています。これだけITサービスの市場拡大が見込まれている中で、欠かすことのできないITインフラに携わるインフラエンジニアの需要は、すぐになくなるということは考えにくく、将来性がある職種と言えるでしょう。

また、IDCJapanが発表した国内ITインフラサービス市場の調査では、2021年~2026年の間、成長率は上昇傾向が続くと予測されました。新型コロナウイルス感染症の拡大により普及したリモートワークやDX推進に伴い、ITインフラ関連のニーズが拡大していることが背景にあると見ています。クラウドやVDI(デスクトップ仮想化)など、新しい技術の需要も継続していますので、求められる技術を身に着けていくことで、今後もインフラエンジニアとしての市場価値は高まっていくでしょう。
参考:IDC|国内ITインフラストラクチャサービス市場予測を発表
 検索エンジンで「インフラエンジニア」のキーワード検索をすると、「やめとけ」や「きつい」、「つまらない」などの関連用語が出てきますが、なぜそのようなマイナスイメージを持たれるのでしょうか。
検索エンジンで「インフラエンジニア」のキーワード検索をすると、「やめとけ」や「きつい」、「つまらない」などの関連用語が出てきますが、なぜそのようなマイナスイメージを持たれるのでしょうか。
その理由はいろいろ考えられますが、インフラエンジニアの業務である運用・保守・監視においてはマニュアル通りの単調な作業になりがち、トラブル発生時には休日・夜間関係なく対応しなければならない点などが意見として多いようです。また、インフラエンジニアの活躍は、表立って評価されることが少ないことなども理由としてあげられます。
「きつい」「つまらない」と感じるようであれば、裏方としてITサービスを支えていることに自信を持ち、転職も視野に入れながらキャリアアップするための向上心をもって取り組むことが大切です。
少しでも転職の成功率を上げたいのであれば、ネットワークやサーバー、セキュリティやクラウドなどの基礎知識を習得しておくことが有効です。インフラエンジニアになるのに、絶対必要な資格というものはありませんが、資格試験の勉強を通して基礎知識を習得することが可能ですので、ここでは、インフラエンジニアを目指している人におすすめしたい資格を3つご紹介します。
Linuxとは、WindowsやMacOSといったOSの一種で、サーバー管理によく使用されるOSです。
LinuCは、Linuxに関する知識や技術力を証明できる民間資格であり、サーバー系の知識習得を目指している人におすすめすの資格となります。サーバーの構築・運用だけでなく、クラウドやオープンソースのリテラシー、システムアーキテクチャの知見など、資格取得を目指しながら最新の知識を習得することが可能です。LinuCは、レベル1〜3まであり、レベル1であれば初心者でも1ヶ月から3ヶ月程度勉強すれば取得可能で、未経験でも挑戦しやすい資格と言えるでしょう。
CCNAは、ネットワーク機器ベンダーのシスコシステムズが主催している認定資格です。 資格取得とともにネットワークの基礎などを学べるため、ネットワーク系の知識習得を目指している人におすすめの資格です。ネットワークの基礎以外にも、ネットワークアクセスやセキュリティの基礎、IP接続・IPサービス、自動化およびプログラマビリティなどの知識を身につけることができます。ネットワーク系の資格では比較的初級レベルで、初心者であれば個人差はあるものの1ヶ月程度勉強すれば取得可能と言われています。
ORACLE MASTERは、日本オラクルが運営する認定資格の一つで、Oracle Database(オラクルデータベース)の管理スキルを証明することができます。ORACLE MASTERの受験勉強を通して、体系的にデータベース技術者に必要なスキルを習得することが可能なので、データベースの知識習得を目指している人に向いている資格と言えるでしょう。レベル別にデータベースの基礎知識からSQLの知識全般まで習得できるので、段階を踏んでレベルアップすることが可能です。
未経験からインフラエンジニアになりたい場合、具体的にどのような方法があるのか分からずに悩んでいる人もいるでしょう。ここでは、未経験からインフラエンジニアを目指すための学習方法と就職活動について、具体的な方法をご紹介します。
インフラエンジニアに必要な基礎知識の習得は独学でも可能であり、学習方法には書籍やオンライン学習サイト・学習アプリなどがあります。独学のメリットは、自分のペースで勉強を進めることができ、費用も比較的安価に抑えられることですが、デメリットとしては周囲からの影響がなく挫折しやすいということが挙げられます。
書籍で独学する場合、いきなり専門性の高い内容の参考書を選んでしまうと、理解できずに勉強が嫌になってしまうリスクがあります。イラストや多くのカラーが使われていて見やすく、専門用語が簡単な言葉で説明されているような、自分のレベルに合った書籍から始めましょう。自分に合った書籍が見つかれば、書籍の内容にそって実際に手を動かしてみることが大切です。書籍によって得られる知識を実践できる環境を作り、アウトプット学習を行ってください。
また、今ではオンライン学習サイトも数多く存在します。おすすめの書籍やオンライン学習サイト、アウトプット学習を行うための方法については、次の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
インフラエンジニアになるためには、学習と並行して、就職・転職活動を行う必要があります。未経験者であれば、求人検索サイトに出てくる数多くの求人案件について、比較方法がわからずに困ってしまう人もいるでしょう。
求人の見つけ方が分からない人は、転職エージェントを利用するというのも一つの手です。エージェントは就職先に求める希望条件を上手に引き出し、求める条件に合った企業を探しだしてくれます。また、面接対策や書類へのアドバイスなど、採用におけるさまざまなサポートを受けることもできます。
転職エージェントは数多く存在し、それぞれに特色があります。まずはIT業界、ITエンジニアの就職・転職を得意とする転職エージェントを探してみるとよいでしょう。
プログラミングスクールの良いところは、学習に必要な準備がカリキュラムによって用意されていることです。教材選びから学習スケジュールの作成、アウトプット学習を行うための環境構築まで、就職のための学習を効率的に行うことができます。また、挫折の大きな要因となる「わからないところを聞ける人がいない」という問題を解消できるため、挫折リスクも低減することができます。
ITスクールの中でも、インフラエンジニアを目指せるコースを設けているところであれば、インフラエンジニアに必要なサーバーやネットワーク、クラウドやセキュリティなどの基礎知識からLinuxやAWSなどのスキルを集中的に習得することができます。
就職支援も行っているITスクールであれば、転職エージェントと同じような就職サポートを、学習と並行して受けることもできます。
 就職直結型・完全オンライン学習のプログラミングスクール「学舎さくら」では、プログラマを目指す「プログラミング専攻」とインフラエンジニアを目指す「インフラ専攻」の2つのコースをご用意しています。ここでは、「インフラ専攻」コースについてご紹介します。
就職直結型・完全オンライン学習のプログラミングスクール「学舎さくら」では、プログラマを目指す「プログラミング専攻」とインフラエンジニアを目指す「インフラ専攻」の2つのコースをご用意しています。ここでは、「インフラ専攻」コースについてご紹介します。
学舎さくらのカリキュラムなら、最短2ヶ月で初心者からインフラエンジニアを目指せます。
Linux、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、PostgreSQLなど基礎から実践まで 80以上の教材、100以上の問題集を揃えています。
紹介企業様の紹介料で運営しているため、受講料は無料です。途中でやめても解約金や違約金なども一切発生しません。テキスト代なども不要です。
通常、Linux試験の「LinuC」の受験には、16,500円(税込)の受験料が必要となりますが、学舎さくらの受講生は、一定条件を満たすことでLinux試験の「LinuC」を無料で受験することが可能です。
完全オンラインによる学習なので、パソコン1台と通信環境さえ整っていれば全国どこからでも受講できます。また、毎月入学を受け付けているので、思い立ったときに説明会に参加することが可能です。
プロの講師陣があなたの「分からない」に答えます。チャットツールを通じていつでも質問できるので、初心者でも安心して受講いただけます。
また、マンツーマンでキャリアアドバイザーが書類の添削や面接対策、企業紹介まで就職サポートを行います。首都圏を中心に3500社以上の就職紹介先がありますので、キャリアアドバイザーと二人三脚で自分に合った企業を探していくことが可能です。
インフラエンジニアは、将来性のあるIT業界にとって欠かせない職業であり、魅力となるメリットもたくさんある仕事です。自分が向いているかどうかを考えたい場合は、インフラエンジニアがどのような仕事をしているのかを理解しておきましょう。勤務体制やきついと感じそうな業務の特徴、キャリアアップのために必要な努力などを知ることで、自分に合っているかどうかを考えることができます。
学習に自信がなくて迷っている人は、ぜひ「学舎さくら」のインフラ専攻を受講を検討してみてください。学習だけでなく、就職サポートも行っていますので、就職・転職を一緒に目指すことができます。入学は毎月受け付けているので、まずはWeb説明会に参加してみてくださいね。
最新記事
プログラミング学習に暗記は不要!未経験から効率的に学習する方法
2024年4月18日
この記事の目次1 【結論】プログラミング学習に暗記は必要ない1.1 【理由1】すべて暗記するのは不可能なため1.2 【理由2】カンニングしてもいいため1.3 【
プログラミングに必要なパソコンのスペックとは?初心者向けの選び方
2024年4月18日
プログラミングには、最低限のスペックを備えたパソコンが必須です。とはいえ、初心者の人は「プログラミングに必要なパソコンのスペック」を把握していないでしょう。今回
インフラエンジニアのやりがい5選!向いている人や一日の仕事の流れも解説
2023年10月20日
ITエンジニアのなかでもインフラエンジニアに興味を持っており、「どのようなやりがいがあるのだろう?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。 type転職
